「簿記2級の連結会計、難しすぎる…」
「勉強しても全然理解できない」
「もういっそ捨ててしまおうか…」
そんなふうに悩んでいる人は多いはずです。連結会計はもともと簿記1級の範囲だったこともあり、独学で勉強しているとハードルが高く感じるのは当然です。でも、本当に全部捨ててしまって大丈夫でしょうか?
実は、連結会計を完全に捨てると合格が厳しくなるのが現実。とはいえ、満点を狙う必要はありません。ポイントを押さえて効率よく学習すれば、適切な対策で10点以上取ることも可能です。
この記事では、連結会計を「最小限の努力で得点源にする方法」を解説します。捨てるのではなく、コスパよく学ぶのが合格への近道。短時間で最大の成果を得る勉強法を知りたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
- 簿記2級に合格するために、連結会計の対策がどこまで必要かがわかる
- 「連結会計は難しい」は本当か?試験問題から読み解く実態
- 限られた時間でも効率よく得点するための連結会計の学習法
この記事を書いている私は、2022年6月に日商簿記2級を受験。88点で合格しました。
ちなみに、私の日商簿記2級の勉強方法は、市販本とアプリ、オンライン講座です。

\お申し込みはこちらから/
簿記2級の第2問連結会計は捨てるほど難しいのか?



簿記2級の連結会計は「難しい」とよく言われます。確かに他の商業簿記の分野と比べると処理が複雑で、独学で学ぶにはハードルが高い部分もあります。しかし、実際の試験ではパターン化された問題が出題されるため、すべてを完璧に理解しなくても、要点を押さえれば得点を狙えます。以下では、連結会計が難しいと言われる理由や試験の出題傾向を分析し、本当に捨てるべきかどうかを考えていきます。
連結会計が難しいと言われる理由
連結会計が難しいと言われるのは、処理の手順が多いことが大きな理由です。通常の仕訳だけでなく、子会社の取り込み、内部取引の相殺、非支配株主持分の計算など、他の商業簿記にはない特有の処理が必要になります。
さらに、連結会計の概念は日常生活ではなじみがなく、イメージしづらいことも難易度を上げている要因です。ただし、すべての論点を深く理解する必要はなく、出題頻度の高い処理に絞って学習すれば、効率よく得点することが可能です。
難しく感じるのは、何から手をつければいいのか分からない状態だからであり、学習のポイントを押さえればハードルは下がります。
実際の試験問題を分析
簿記2級の試験で出題される連結会計の問題は、基本的な計算を問うものが中心です。たとえば「親会社と子会社の合算」「内部取引の消去」「非支配株主持分の計算」など、出題パターンはある程度決まっています。そのため、過去問や予想問題を繰り返し解けば、短期間の学習でも十分に得点できるのです。
また、最近の試験では連結会計が必ずしも出るわけではなく、他の分野が出題されることもあります。つまり、苦手意識を持ちすぎず、最低限の得点を取るための勉強をしておけば、合格点には十分到達できるということです。
「連結会計が難しい」というのは勘違い
連結会計が難しく感じるのは、全範囲を完璧に理解しようとするからです。確かに、すべてを細かく理解しようとすると時間がかかりますが、試験で問われるのはごく一部です。たとえば「基本的な仕訳」「相殺消去」「財務諸表の作成手順」など、決まった論点を押さえるだけでも得点できます。
また、短期間で10点以上取ることは十分可能なので、苦手だからといって完全に捨てるのはもったいないのです。「連結会計は難しい」というのは、実は勉強の仕方を間違えているだけ。無理なく部分点を取る戦略を立てることで、合格に近づくことができます。
簿記2級に合格するために連結会計の対策は必要
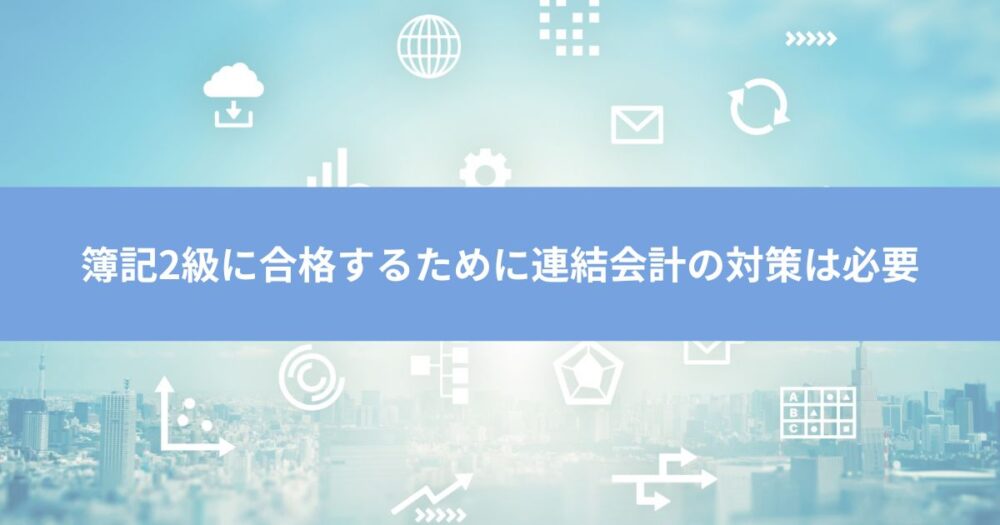
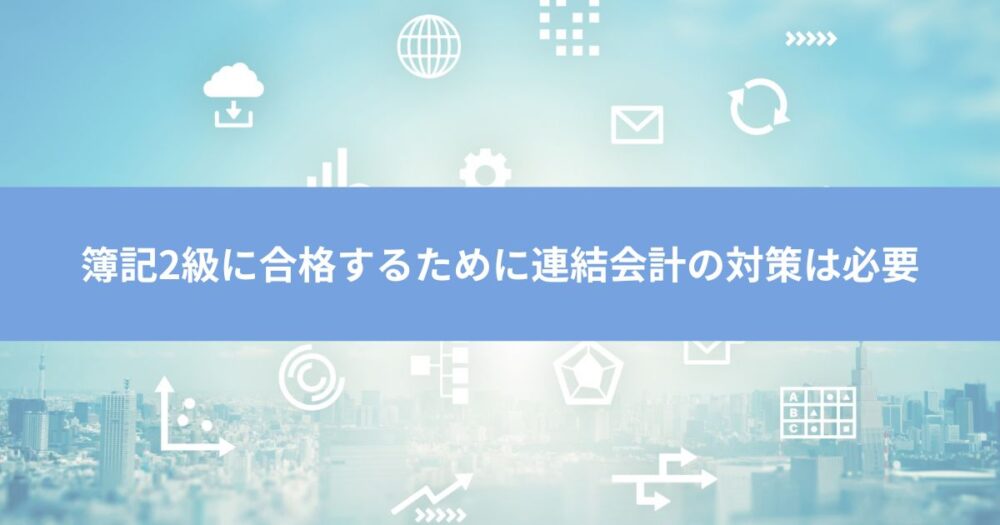
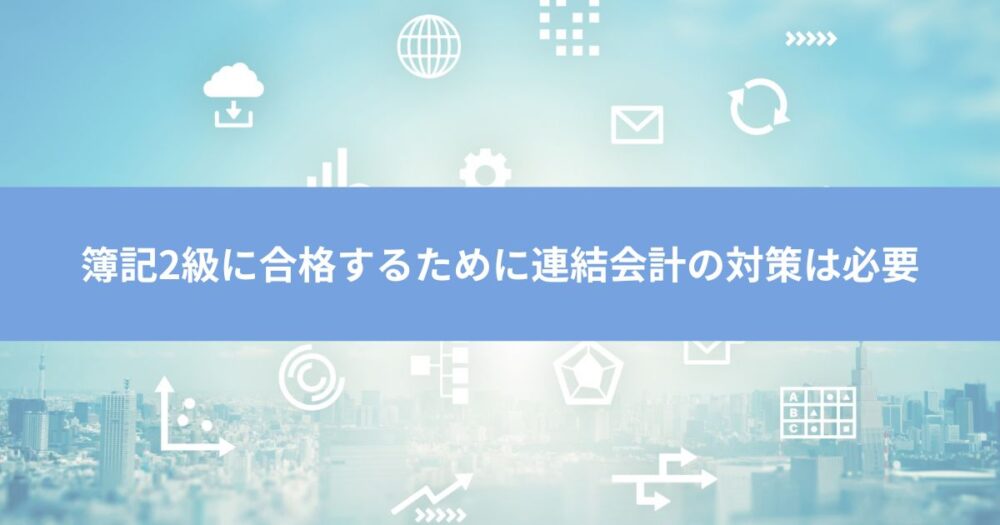
簿記2級の受験生にとって、連結会計は「捨てるべきか」「対策するべきか」の判断が難しい分野です。連結を完全に捨てても合格は可能ですが、完全に捨てるのはリスクが高いです。逆に、最小限のポイントを押さえておくだけで、合格の可能性を大きく引き上げることができます。以下では、連結を全く勉強しない場合のリスクと、部分的に対策するメリットについて解説します。
連結を全捨てしても合格は可能
連結会計を完全に捨てても簿記2級には合格できます。ただし、他の問題で確実に70点以上取る必要があり、リスクが高いのが実情です。簿記2級の試験は100点満点中70点で合格となりますが、連結会計が含まれる第2問の配点は10〜20点。これを完全に捨てると、他の分野で満点近く取らなければならず、思わぬ難問に当たった場合の影響が大きくなります。
実際に「工業簿記が予想以上に難しかった」「商業簿記の仕訳問題で失点した」といった理由で、あと数点足りずに不合格となるケースも多いです。リスクを分散する意味でも、完全に捨てるより、最低限の対策をしておいた方が安全です。
連結を部分的に対策するメリット
連結会計は、すべてを理解する必要はありませんが、ポイントを押さえておくだけで試験本番の得点を底上げできます。連結の問題はある程度パターンが決まっており、基本的な仕訳や合算処理を覚えるだけで5〜10点を取ることが可能です。たとえば、親会社と子会社の合算、内部取引の相殺消去、非支配株主持分の計算など、出題頻度の高い項目に絞って学習すれば、短期間の対策でも十分に戦えます。
また、過去問を見ても、全く手をつけていないと解けない問題でも、少し知識があれば部分点をもらえる問題が多いのが特徴です。試験の合格率を上げるためにも、最低限の連結対策はやっておくべきでしょう。
完全に捨てずに最低限の対策をすべき
簿記2級に合格するためには、連結会計を完全に捨てるのではなく、最低限の部分だけ対策するのが賢い戦略です。確かに、連結は初見では難しく感じますが、基本のルールを理解すれば、短時間で点を取れるようになります。たとえば、連結の問題が10点分出題された場合、その半分でも取れれば合格ラインに大きく近づきやすいです。
逆に、すべてを捨てると、他の分野で満点に近い得点を取る必要があり、合格の難易度が上がってしまいます。試験の出題傾向を考えれば、完全に捨てるよりも、少しでも得点できる部分を作っておいた方が確実に有利です。合格を目指すなら、連結会計を完全に捨てるのではなく、効率よく学習することをおすすめします。
簿記2級第2問連結会計を効率よく攻略する方法



簿記2級の連結会計は「難しい」と敬遠されがちですが、実は必要最低限の知識だけで得点できるコスパの良い分野です。すべてを完璧に理解する必要はなく、ポイントを絞って学習すれば、短時間の勉強でも合格ラインに届きます。以下では、効率的に連結会計を学ぶ3ステップと、最小限の努力で得点を狙う方法について解説します。「とにかく合格したい」「連結会計に時間をかけたくない」という人は、ぜひ実践してみてください。
3ステップでコスパよく学ぶ
まずは連結会計の基本を押さえます。「連結とは何か」「なぜ必要なのか」を簡単に学ぶだけで、問題の解き方がイメージしやすくなります。
連結会計の出題範囲は広いですが、毎回問われる部分は決まっています。「親子会社の財務諸表の合算」「内部取引の相殺消去」「非支配株主持分」の3つを重点的に対策すれば、最短で得点力が身につきます。
簿記2級は70点で合格ですが、連結会計が出る第2問を全問正解する必要はありません。基本的な仕訳や合算処理だけでも5〜10点は取れるので、解ける問題を確実に拾う意識を持ちましょう。
最小限の努力で得点を狙う方法
「連結会計は捨てる」と決めてしまうのはもったいないです。なぜなら、最低限の対策で得点しやすいからです。たとえば、試験では「子会社の財務諸表を親会社と合算する問題」や「内部取引の相殺」など、毎回似たような問題が出題されます。
対策としては、「解ける問題」と「捨てる問題」を明確にすることが重要です。すべてを理解しようとするのではなく、簡単な仕訳や計算問題を優先し、複雑な問題は最初から捨てる判断をすることで、効率的に得点を確保できます。
短時間で連結会計を攻略したいなら、まずは頻出パターンの仕訳を5〜10問解いてみることから始めましょう。それだけで「取れる点」と「捨てる点」がはっきりし、合格に必要な学習量がグッと減ります。
もし独学で連結会計の対策が難しいと感じている場合、下記の記事を参考にしてみてください。
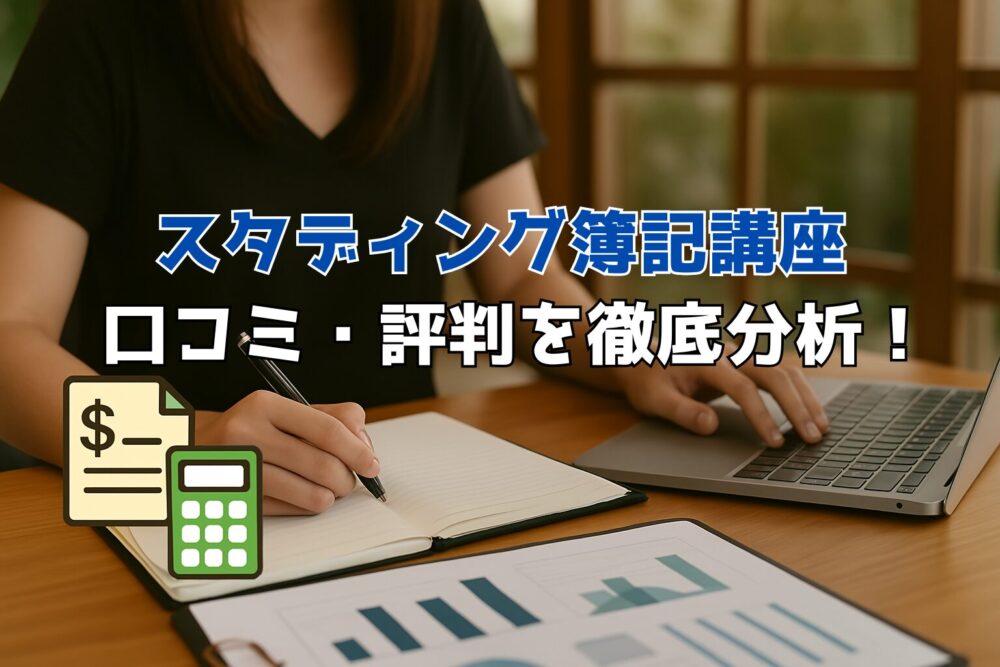
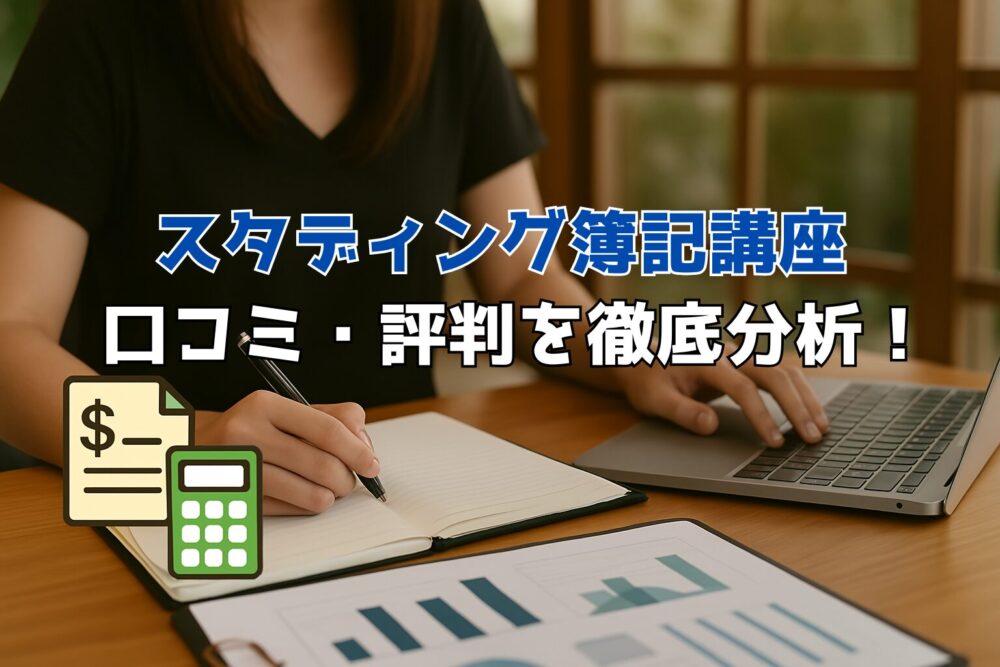
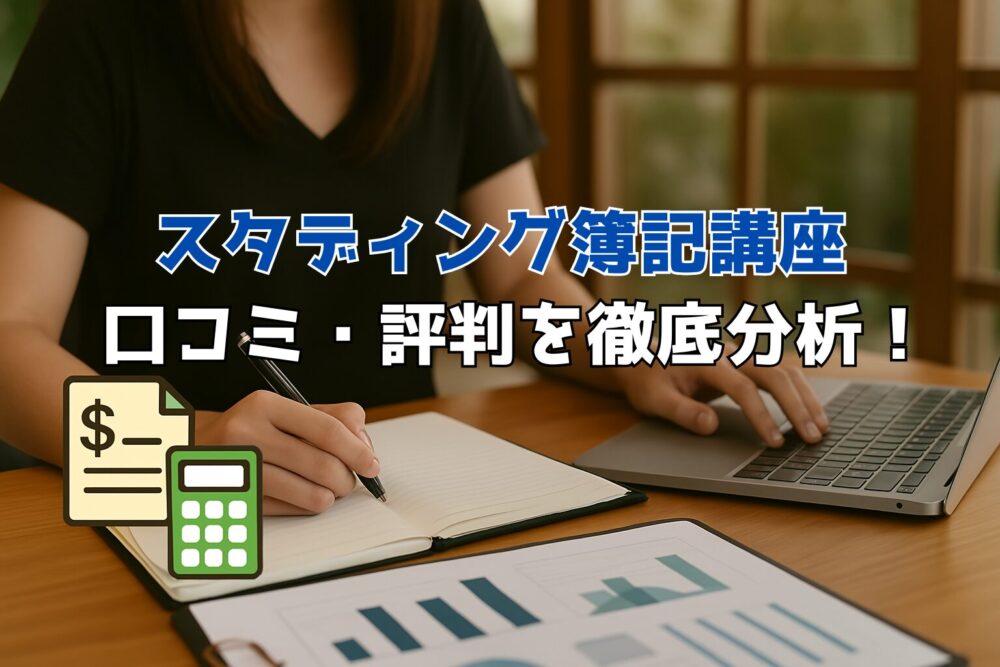



\お申し込みはこちらから/
簿記2級第2問連結会計を捨てる場合のリスク



簿記2級の試験勉強で、「連結会計を捨てるべきか?」と悩む人は多いでしょう。確かに難しい分野ですが、まったく手をつけないのは危険です。なぜなら、連結会計は出題頻度が高く、部分点を狙える範囲だからです。以下では、連結会計を捨てた場合に起こりうるリスクを解説します。合格を確実にするためにも、最低限の対策をする重要性を理解しておきましょう。
合格率が大きく下がる可能性
簿記2級の試験では、70点以上を取らなければなりません。連結会計は第2問で約20点分出題されるため、完全に捨てるとそのぶん得点のチャンスを失います。
連結を捨てる場合、残りの問題でほぼノーミスを目指さなければなりません。しかし、試験本番では予想外のミスや難問に当たることもあります。リスクを考えると、連結の基礎だけでも対策する方が安全です。
「連結は捨てたけど、あと数点足りずに不合格だった…」というケースも多いです。逆に、連結会計で少しでも点を稼いだ人は、他の問題で失点してもカバーできる可能性が高まります。
時間をかけすぎる必要はありませんが、連結の基本だけでも押さえておけば、合格率は確実に上がるでしょう。
出題傾向の変化
数年前までは「連結は捨てても大丈夫」と言われることもありました。しかし、最近の試験では連結会計の出題割合が増加しており、完全に無視するのはリスクが高くなっています。
簿記2級の試験は、実務に即した内容へと変わりつつあります。とくにネット試験では連結会計が頻出しており、避けることが難しいです。そのため、従来の「連結は捨ててもOK」という考え方は通用しなくなってきています。
過去問を見ると、連結会計の出題は「基本的な修正仕訳」「親子会社の資本合算」「内部取引の相殺」といったパターンが決まっていることが分かります。つまり、全部を完璧に理解しなくても、最低限の対策で部分点を取ることが可能です。
試験の流れを考えると、連結会計を捨てるよりもポイントを絞って学習し、最低限の得点を狙うほうが圧倒的に有利です。
まとめ:「簿記2級合格のカギは、第2問連結会計を「捨てる」のではなく「活かす」こと」



簿記2級の合格を目指すなら、連結会計を「完全に捨てる」という選択はリスクが大きいです。確かに難しく感じる分野ですが、実はポイントを押さえれば短時間で得点源にできます。
試験の出題傾向を考えると、連結会計の基礎的な部分を理解するだけで10点以上の得点が可能です。とくに、親会社と子会社の資本合算や内部取引の消去といった基本的な仕訳ができれば、部分点を積み重ねることができます。一方で、連結を完全に捨てると、他の問題で高得点を狙わなければならず、合格のハードルが上がります。
最短で合格したいなら、連結会計を「必要最低限」学習し、効率よく得点することが重要です。難しく考えすぎず、シンプルな仕訳から取り組みましょう。
\お申し込みはこちらから/








