「簿記2級に何度も挑戦しているのに、また不合格だった…」そんな悔しい思いをしていませんか?
- 何回受験しても合格できず、もう諦めようかと考えている
- それなりに勉強しているはずなのに、毎回あと数点足りない
- 何が原因なのかわからず、勉強の仕方に自信が持てない
簿記2級は決して簡単な試験ではありません。一発合格できる人もいますが、何度も落ちるのは珍しいことではないのです。ただ、受かる人と落ちる人には、明確な違いがあります。
「どこが間違っているのか」「どうすれば合格できるのか」その答えを知らずに、やみくもに試験を受け続けても、結果は変わりません。
「どこが間違っているのか」「どうすれば合格できるのか」その答えを知らずに、やみくもに試験を受け続けても、結果は変わりません。この記事では、簿記2級に何度も落ちる人の共通点や、合格に必要な正しい勉強法を詳しく解説します。次こそ合格を勝ち取りたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
 Tatsuo
Tatsuo日商簿記2級、3級に何回も落ちたら辛いですよね・・・
でも正しく勉強すれば大丈夫!
この記事を書いている私は、2022年6月に日商簿記2級を受験。88点で合格しました。
ちなみに、私の日商簿記2級の勉強方法は、市販本とアプリ、オンライン講座です。



\お申し込みはこちらから/
簿記2級に何回も落ちる人の特徴とは?



簿記2級は簡単な試験ではなく、私のように何度も挑戦してやっと合格する人も多いです。しかし、同じように受験を続けても結果が変わらないのは、「勉強のやり方」に問題がある可能性が高いです。実際、簿記2級に何度も落ちる人には、いくつか共通する特徴があります。
勉強時間を確保しているのに結果が出ない、努力しているのに点数が伸びないという人は、以下で紹介するポイントに当てはまっていないか確認してみてください。合格するためには、まず「なぜ受からないのか」を明確にすることが大切です。
簿記3級の基礎が身についていない
簿記2級の試験では、3級で学んだ内容を前提に問題が作られています。そのため、3級の知識があやふやなままだと、2級の問題が理解できず、スムーズに解答できません。たとえば、仕訳のルールや貸借対照表・損益計算書の構造を正しく理解していないと、決算整理の問題でミスをしやすくなります。
また、3級の精算表や財務諸表の作成に苦手意識がある人は、2級の応用問題で手が止まることが多いです。3級の学習が不十分なまま2級に挑戦すると、基礎的な部分でつまずき、問題が解けない原因になってしまいます。もし3級を十分に理解できていないと感じたら、まずはテキストを読み直し、基本の仕訳や財務諸表の作成を復習しましょう。
工業簿記が苦手で得点が取れない
簿記2級では、商業簿記と工業簿記の両方が出題されます。商業簿記に比べて工業簿記は馴染みがなく、苦手意識を持つ人が多いのですが、実は「パターンを覚えれば得点源になる分野」です。
工業簿記の問題は、製造原価の計算や標準原価計算などが中心で、計算の流れを理解すれば比較的得点しやすいのが特徴です。しかし、理解せずに「なんとなく計算している」状態だと、本番で少し問題の形が変わっただけで解けなくなってしまいます。
工業簿記を克服するには、基本的な計算手順をしっかり覚え、練習問題を繰り返し解くことが重要です。とくに、過去問を解く際には、解き方のプロセスを意識し、公式や計算式の意味を理解することが合格への近道になります。
問題演習が不足している
テキストを読むだけで「勉強した気」になっていませんか? 簿記2級では、知識をインプットするだけではなく、実際に問題を解いてアウトプットすることが不可欠です。試験本番では、限られた時間の中で問題を解かなければならず、知識があってもスムーズに処理できなければ合格は難しいでしょう。
とくに、仕訳問題や決算整理のような問題は、数をこなすことでパターンを理解し、瞬時に対応できるようになります。過去問や予想問題を繰り返し解き、試験で出題される形式に慣れておくことが大切です。
また、ただ問題を解くだけではなく、「なぜこの解答になるのか」をしっかり理解することが重要です。間違えた問題は必ず見直し、解き方を説明できるレベルまで復習しましょう。演習を積むことで、試験本番でも落ち着いて対応できる力がついていきます。




一般的に日商簿記2級に合格に必要な時間は、独学であれば250時間〜350時間です。合格ができない場合、そもそもの勉強時間が足りていない可能性があります。



ネット試験の出題傾向に慣れていない
簿記2級には、従来の筆記試験(ペーパー試験)と、パソコンで受験するネット試験(CBT方式)があります。最近はネット試験を選ぶ人も増えていますが、「事前にネット試験の操作に慣れておかないと、本番で戸惑ってしまう」ことも多いです。
ネット試験では、問題の表示方法が筆記試験とは異なり、問題の見直しがしにくかったり、メモを取るスペースがなかったりといった違いがあります。また、電卓の使い方や入力ルールも決められているため、操作ミスで本来取れるはずの点数を落としてしまう人もいます。
ネット試験を受験する場合は、事前に模擬試験や公式の練習ツールを使って、画面の操作や問題の形式に慣れておきましょう。また、試験当日に焦らないためにも、「ネット試験ではどんな問題が出るのか」「どういう順番で解いていくべきか」をシミュレーションしておくことが大切です。
時間配分がうまくできていない
簿記2級の試験は制限時間があり、時間内にすべての問題を解き切ることが求められます。しかし、時間配分を考えずに試験に臨むと、1問に時間をかけすぎてしまい、後半の問題に手がつかないという事態になりがちです。
たとえば、第1問の仕訳問題に時間をかけすぎると、配点の高い第3問や第5問に十分な時間を使えず、合格点に届かなくなってしまいます。とくに、難しい問題にこだわりすぎると、解ける問題を見落としてしまい、結果的に得点が伸びません。
試験では、「時間を決めて解く」という意識が重要です。たとえば、「仕訳問題は15分以内、第2問・第3問は20分ずつ、第4問・第5問は15分ずつ」など、自分なりの時間配分を決めておくと、焦らずに解答できます。また、試験本番では「わからない問題は一度飛ばし、最後に時間があれば見直す」という戦略も有効です。
時間配分を意識することで、試験本番でも落ち着いて問題を解き、確実に得点を積み重ねることができます。試験前の模擬演習で時間を測りながら問題を解く習慣をつけると、本番でもスムーズに進められるでしょう。
\お申し込みはこちらから/
簿記2級に何度も落ちる人がやりがちな間違った勉強法
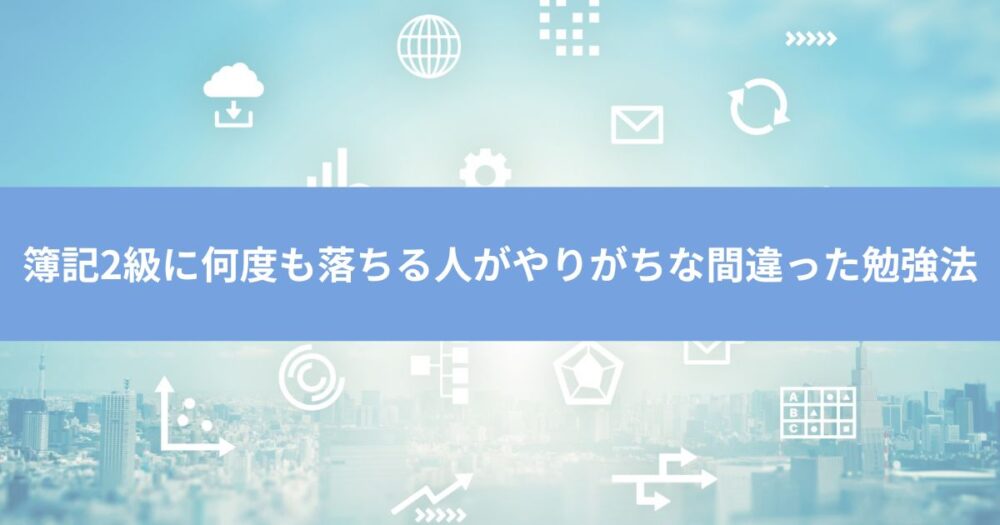
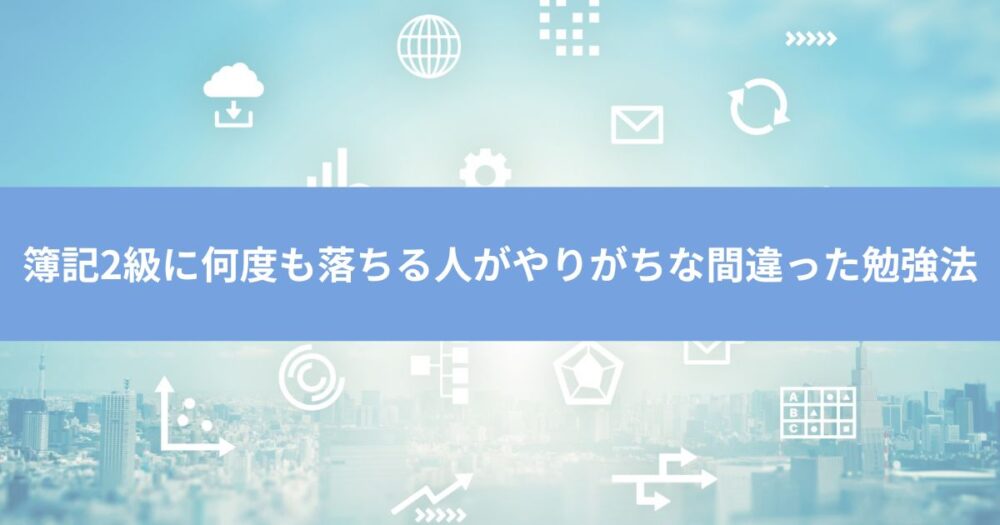
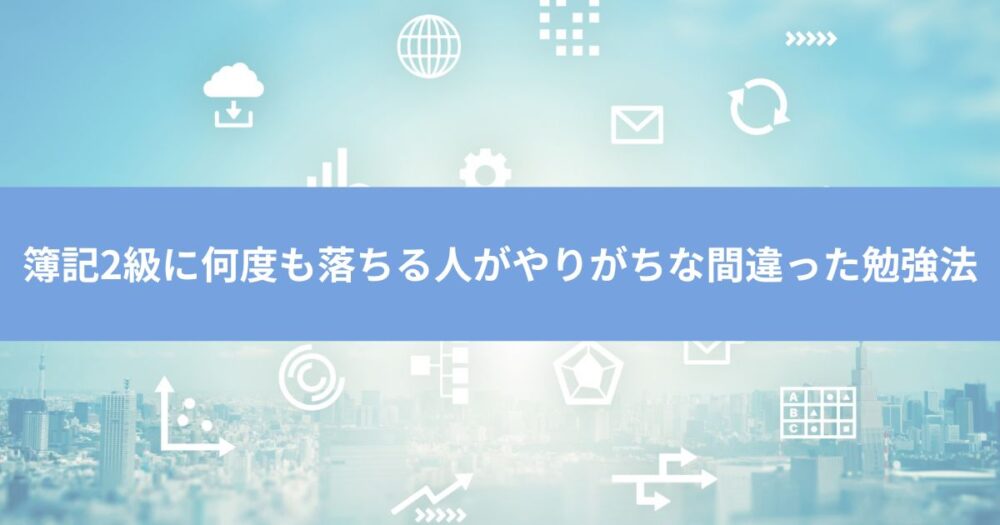
「簿記2級に何度も挑戦しているのに、また不合格だった…。」そんな状況が続くと、「自分には向いていないのかも」と落ち込んでしまいます。しかし、何度受けても受からないのは、単に勉強方法が間違っているだけかもしれません。簿記2級は、しっかりとした対策をすれば必ず合格できる試験です。重要なのは、正しい方法で効率よく学ぶことです。以下では、簿記2級に落ちる人がついやってしまいがちな間違った勉強法を3つ紹介します。当てはまるものがないか、ぜひ確認してみてください。
過去問だけを解いて満足している
「過去問を何回も解いているのに合格できない…」こんな悩みを持っている人は多いのではないでしょうか?過去問を解くことは確かに重要ですが、それだけで十分とは言えません。簿記2級の試験は、毎回異なる出題がされるため、過去問の暗記では通用しないからです。
近年の簿記2級は、過去問と同じ問題がそのまま出ることはほぼなく、応用力を求められる出題が増えています。「この仕訳パターンはこうだから、同じ問題が出れば解ける」と考えていると、少し形式が変わっただけで対応できなくなるのです。
たとえば、工業簿記の標準原価計算で、過去問では「材料費の計算方法」が問われていたとします。しかし、本番では「労務費の計算」を求められることがあります。過去問のパターンだけを覚えていると、「労務費はどう計算すればいいのか?」と手が止まってしまうのです。
過去問は、「試験の傾向をつかむもの」として活用し、応用力を鍛えるための演習もしっかり行うことが大切です。単なる暗記ではなく、問題の本質を理解する意識を持ちましょう。
丸暗記に頼ってしまう
「とにかく仕訳を覚えれば何とかなる」「テキストに載っている解答を暗記しておけば大丈夫」このように考えて勉強していると、試験本番で痛い目を見ることになります。簿記2級の試験は、暗記だけでは対応できない問題が多く、理論をしっかり理解していないと応用が利かなくなるからです。
簿記の試験では、ただ仕訳の形を覚えているだけでは太刀打ちできません。たとえば、貸倒引当金の問題で「売掛金の〇%を計上する」と過去問で学んでいたとします。しかし、試験本番では「貸倒引当金の繰入額を求めなさい」という別の形で問われることがあります。このとき、「貸倒引当金の繰入とは何か?」を理解していないと、解き方がわからず、焦ってしまうでしょう。
また、工業簿記の問題では、「直接材料費」や「加工費」の意味を理解せずに覚えていると、少し複雑な問題が出たときに対応できません。丸暗記ではなく、「なぜこの処理が必要なのか?」を考えながら学ぶことが重要です。
簿記は理論と実務に基づいた試験です。ただ暗記するのではなく、取引の流れや仕組みを理解しながら学習することで、初見の問題にも対応できる力がついていきます。
参考書を次々に変えてしまう
「この参考書は自分に合わないかも…」「もっとわかりやすい本があるのでは?」と、次々に新しい参考書に手を出していませんか?一見、効率的に思えるこの方法ですが、実は逆効果です。簿記2級の学習では、1冊の参考書を徹底的に使い込むことが、合格への近道なのです。
参考書ごとに解説の仕方や重点の置き方が違うため、複数の本を使うと知識が分散し、混乱する原因になります。また、新しい参考書に変えるたびに「前の本で学んだ部分をまた最初からやり直す」ことになり、時間のロスが大きくなってしまいます。
たとえば、最初に使っていた参考書では「工業簿記の標準原価計算」の説明がわかりにくかったとします。「もっとわかりやすい本があるかも」と別の本に変えると、今度は商業簿記の解説が違ったり、解説の流れが変わってしまったりして、学習がスムーズに進まなくなります。結果的に、どの参考書の内容も中途半端になり、知識の定着が遅れてしまうのです。
重要なのは、1冊を何度も繰り返して、自分のものにすること。どうしても理解できない部分があれば、ネットで調べたり、YouTubeの解説動画を活用するのもおすすめです。最初に選んだ参考書を信じて、何度も繰り返し読み込みましょう。
\お申し込みはこちらから/
簿記2級に合格するための効果的な勉強法
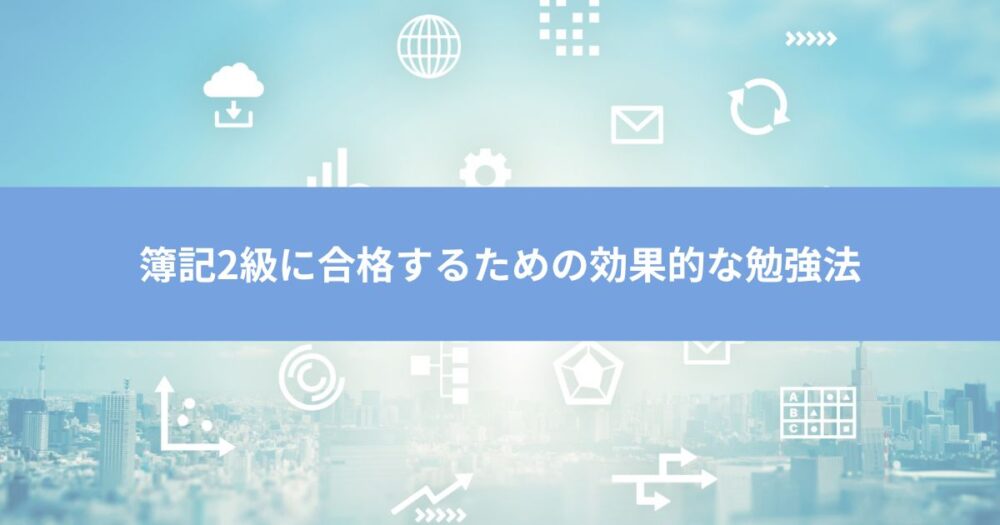
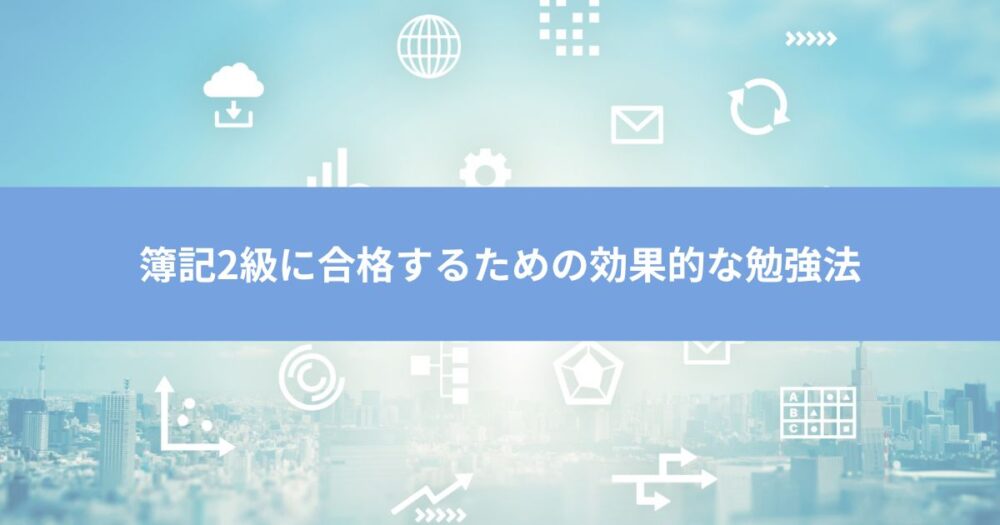
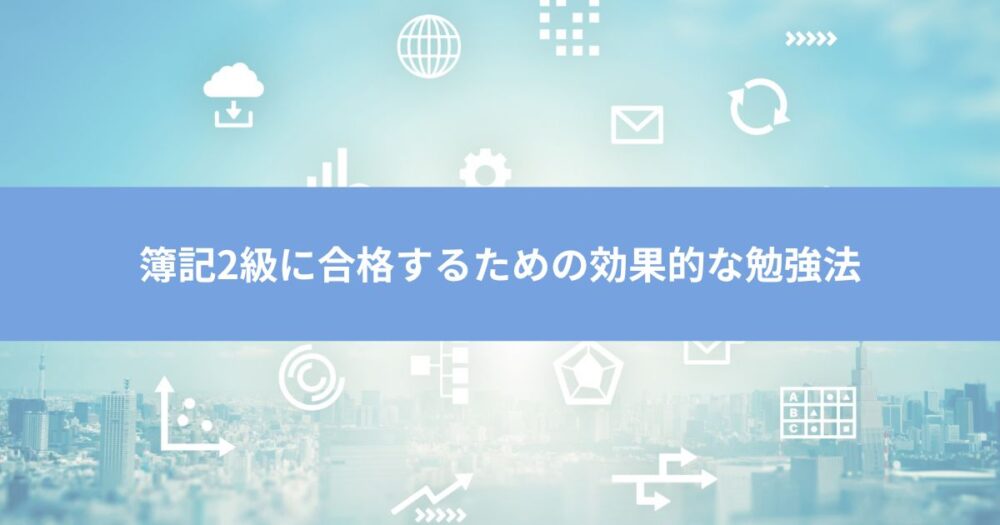
簿記2級の試験は難易度が高く、独学ではなかなか合格できないと感じる人も多いでしょう。しかし、正しい勉強法を実践すれば、効率よく学習を進め、合格へと近づくことができます。大切なのは、「基礎の徹底」「継続的な問題演習」「実践形式の対策」をバランスよく取り入れることです。ただ闇雲に勉強するのではなく、合格者が実践している効果的な方法を取り入れましょう。以下では、簿記2級に合格するための具体的な勉強法を詳しく解説します。
簿記3級の知識を完璧にしておく
簿記2級に合格するためには、まず簿記3級の知識をしっかりと固めることが最重要です。3級の内容が曖昧なままだと、2級の問題が理解できず、応用問題にも対応できません。
簿記2級は、簿記3級の基礎知識を前提として問題が作られています。3級の段階で仕訳や財務諸表の基本が定着していないと、2級の試験では「なぜこの処理をするのか?」といちいち考える時間がかかり、スムーズに解答できません。とくに、決算整理仕訳や精算表の知識は2級の問題を解く際に必須となるため、基礎が不十分なまま進めると合格は難しくなります。
たとえば、3級で学ぶ「売掛金と買掛金の違い」がしっかり理解できていないと、2級の「決算整理仕訳」で手が止まってしまいます。また、貸借対照表や損益計算書の構造を理解していないと、財務諸表作成の問題に対応できません。
2級の学習を始める前に、まずは3級の内容を完璧に理解することが合格への近道です。3級のテキストを見直し、仕訳や財務諸表の構造をしっかり復習しましょう。
工業簿記は「慣れ」が大事
工業簿記は最初こそ難しく感じるかもしれませんが、解き方のパターンを覚え、繰り返し演習することで確実に得点源にできます。
商業簿記に比べ、工業簿記は出題のバリエーションが少なく、基本的な計算パターンを理解すれば、スムーズに解けるようになります。とくに、原価計算や標準原価計算などの分野は、計算方法さえ理解してしまえば安定して点数が取れるため、苦手意識を持たずに取り組むことが重要です。
たとえば、「材料費」「労務費」「経費」の計算では、公式や基本ルールを覚えるだけで、ほとんどの問題に対応できます。また、製造間接費の配賦に関する問題も、ルールを理解してしまえば計算手順が決まっているため、対策しやすい分野です。
工業簿記は「慣れ」が全てです。最初は難しく感じても、繰り返し演習することで確実に点数を取れるようになります。苦手意識を克服し、毎日少しずつ問題を解く習慣をつけましょう。
参考書は1冊に絞って繰り返し学習
簿記2級の学習では、参考書を何冊も買い漁るより、1冊を繰り返し徹底的に使い込むことが重要です。
参考書ごとに解説のスタイルや重点の置き方が異なるため、複数の本を使うと知識が分散し、かえって混乱してしまうことがあります。また、新しい本に変えるたびに最初から学び直すことになるため、結果的に勉強の効率が悪くなります。
具体的には、「今使っているテキストがわかりにくい」と感じて別の本に手を出した場合、新しい本でも結局途中で理解に詰まり、また別の本を買う…という悪循環に陥ることがよくあります。一方で、同じ参考書を繰り返し学習すれば、最初は難しく感じた部分も徐々に理解が進み、知識が定着しやすくなります。
1冊の参考書を信じて、何度も繰り返し学習することが合格への最短ルートです。どうしても理解できない部分があれば、ネットや動画講座を活用しながら補強するとよいでしょう。
ネット試験の模擬試験を活用する
CBT方式のネット試験を受験する場合は、事前に模擬試験を受け、試験環境に慣れておくことが不可欠です。
ネット試験では、ペーパー試験とは異なり、問題の出題形式や解答方法に特徴があります。事前に練習しておかないと、試験中に操作に戸惑い、実力を十分に発揮できない可能性があります。
たとえば、ネット試験では画面上で問題を読みながら電卓を操作し、メモを取る必要があります。初めて受験する人はこの形式に慣れておらず、時間をロスすることがよくあります。模擬試験を受けておけば、本番の環境にスムーズに適応でき、余計なミスを防ぐことができます。
ネット試験を受けるなら、必ず模擬試験を活用し、試験の流れや操作に慣れておくことが合格のコツです。
時間管理を意識する
簿記2級の試験では、時間配分を意識し、事前に解く順番や時間を決めておくことが重要です。
試験本番で焦ってしまう原因の多くは、「時間配分のミス」です。1問に時間をかけすぎると、後半の問題に十分な時間を確保できず、解けるはずの問題で失点してしまいます。
具体的には、第1問(仕訳問題)で時間を使いすぎると、第3問(財務諸表問題)や第5問(工業簿記)に影響が出ます。事前に「仕訳は10分以内」「財務諸表は20分」といった目安を決めておくと、スムーズに試験を進められます。
試験前に時間を測って演習し、本番で焦らず解けるようにタイムマネジメントを徹底しましょう。
効率的な学習を独学で勉強を進めていくのは難しいため、オンライン講座などを活用したほうが早期合格しやすいです。
\お申し込みはこちらから/



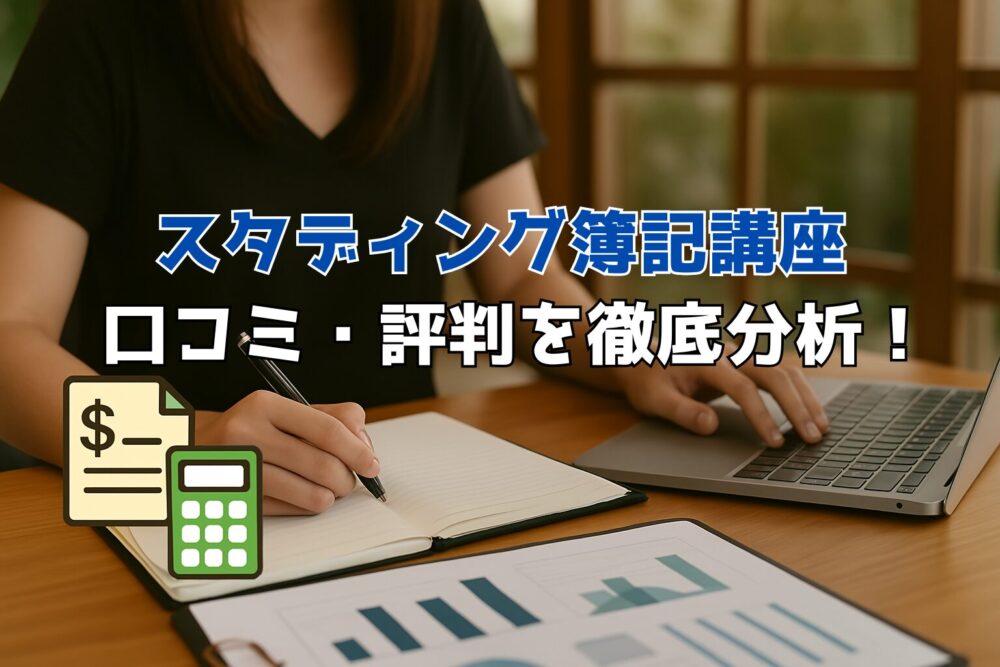
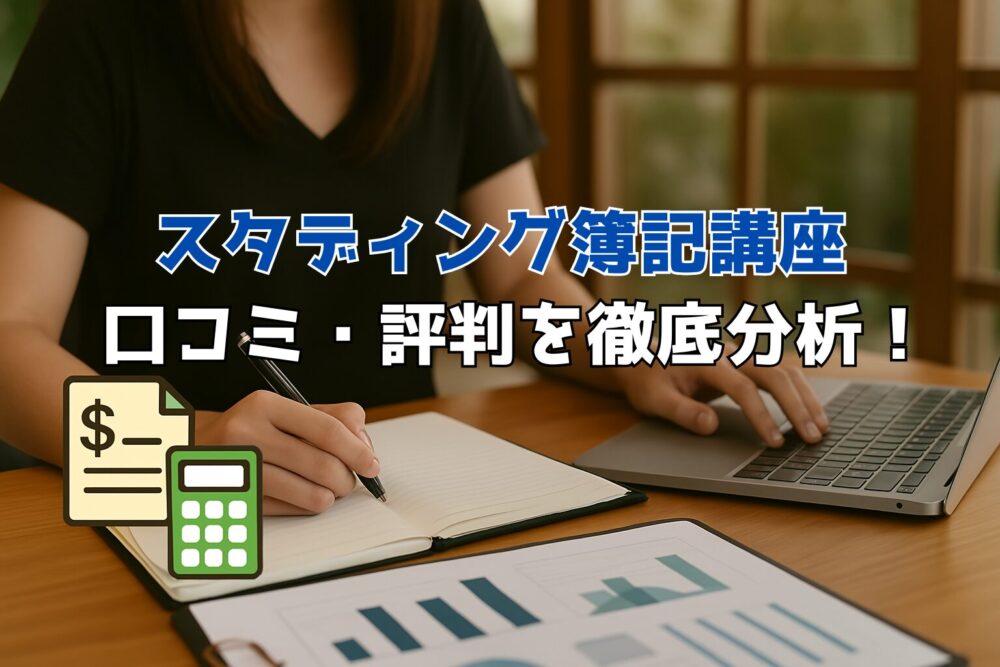
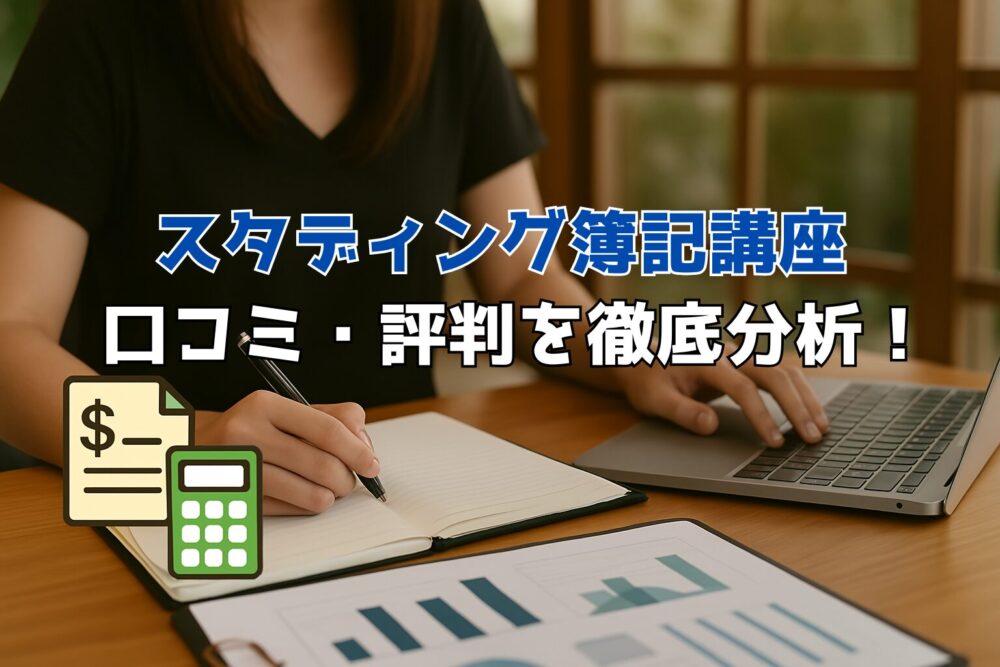
簿記2級に何回も落ちる場合でも諦める必要はない!



簿記2級は決して簡単な試験ではありません。1回で合格できる人もいますが、何度も挑戦してやっと合格する人も多いです。試験に落ちた回数が気になるかもしれませんが、最終的に合格すればその過程は関係ありません。むしろ、繰り返し挑戦することで知識が定着し、合格後の実務にも役立ちます。また、簿記2級の資格はキャリアアップにもつながる重要なスキルです。諦めるのではなく、合格に向けて学習を続けることが大切です。
落ちた回数は気にしなくていい
簿記2級の試験に何回落ちても問題ありません。重要なのは「最終的に合格すること」であり、合格までに何回受験したかを気にする必要はありません。
資格試験は一発合格できることが理想かもしれませんが、受験回数を重ねることで確実に実力がつきます。試験に落ちた経験は、どこが苦手かを知る貴重な機会です。「あと10点足りなかった」「時間配分を間違えた」など、自分の課題が見えてくることで、次の試験に向けた対策を立てやすくなります。また、企業の採用担当者は「簿記2級に何回目で合格したか」までは気にしません。資格を取得していることが重要視されるため、落ちた回数を気にするよりも、合格に向けて前向きに努力を続けることが大切です。
たとえば、3回目で合格した人がいたとして、その間に過去問演習や模擬試験を繰り返していれば、1回目で合格した人よりも深く理解できている可能性があります。また、試験に落ちることで「どう勉強すればいいか」が見えてくるため、結果的に知識の定着度が上がります。
合格までの回数は関係ありません。落ちた経験を活かし、次の試験に向けて効率的な勉強をすれば、必ず合格できます。




履歴書にも日商簿記2級を何回目でどれくらいかかって合格したなんて記載しませんし、5回目で合格しても10回目で合格しても資格の価値は同じです。
簿記2級の合格はキャリアアップにつながる
簿記2級の資格は、経理・会計の仕事を目指す人にとって大きな武器になります。資格を取得することで、転職・就職の選択肢が広がり、キャリアアップの可能性が高まります。
企業にとって、簿記2級を持っている人材は「基本的な会計知識がある」と判断できるため、採用の際にプラス要素になります。とくに、経理や財務の仕事を希望する場合、簿記2級の資格はほぼ必須といえます。また、営業職や総務職でも、会計の知識があることで経営状況を理解しやすくなり、業務の幅が広がることがあります。
さらに、独立やフリーランスで仕事をする場合にも、簿記の知識は役立ちます。個人事業主として帳簿をつける際や、会社の経営に関わる際に、財務の知識があるかどうかで大きな差が生まれます。
たとえば、経理未経験の人が簿記2級を取得したことで、企業の経理部門に転職できたケースは多くあります。また、営業職の人が簿記の知識を身につけたことで、顧客の財務状況を把握しやすくなり、商談がスムーズに進んだという事例もあります。このように、簿記2級は経理職に限らず、さまざまな仕事に活かせる資格です。
簿記2級を取得すると、転職やキャリアアップのチャンスが増えます。試験に落ちても諦めずに挑戦する価値のある資格です。
\お申し込みはこちらから/
まとめ|簿記2級は何回落ちても最終的に合格すればいい



簿記2級の試験に何度も落ちると、「自分には向いていないのでは?」と不安になるかもしれません。しかし、合格するまで挑戦し続ければ、それで十分です。資格試験においては、受験回数よりも「最終的に合格できるか」が重要だからです。
合格までの道のりは人それぞれです。何度か落ちたとしても、その過程で知識が定着し、結果的に実務で役立つスキルが身につくこともあります。むしろ、試験に落ちたことで苦手分野を把握し、次の試験に向けて効率的に対策できるようになります。大切なのは、正しい勉強法を実践し、コツコツ学習を続けること。試験に落ちるたびに学びを得て、確実に実力をつけていけば、必ず合格できます。諦めず、自分のペースで前に進んでいきましょう。




最後まであきらめないことが大事
\お申し込みはこちらから/










